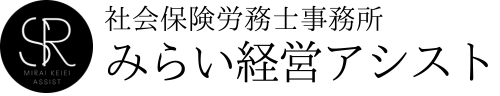処遇改善加算についてご相談を受けていると、「キャリアパスは一応作ったんですが……」という声をよく耳にします。
それだけ、制度そのものが分かりづらく、事業所としても「どこまで作り込むべきか」「何を示せば要件を満たすのか」が判断しにくいのだと感じます。
どんなに見た目のきれいな図や表を作っていても、内容が不十分だったり職員にきちんと伝わっていなければ、要件を満たしているとは言えません。
そのまま放置してしまうと、実地指導での指摘や加算の返還につながるおそれもあります。
本記事では、キャリアパス要件Ⅰで押さえるべき任用要件と賃金体系の“ポイント”を整理します。
ただ、実際に制度や規程へ落とし込むとなると想像以上に難しく、専門的な判断も必要になります。
まずは全体像をつかみ、必要に応じて社労士のサポートも検討してみてください。
目的は「将来のキャリアを見通しやすくすること」
任用要件と賃金体系を整える目的はシンプルです。
- 「この職位になるには、経験○年+この資格+評価結果が必要です」
- 「この等級になると、基本給は○万〜○万円、リーダー手当がつきます」
と、どのような要件を満たせば昇給・昇進・昇格できるのかを明確にすること。
その上で
- 職員は「自分は何に取り組めば次のステップに進めるのか」が分かる
- 事業所は「次の段階で職員にどんな役割を期待しているのか」が自信を持って伝えられる
ここを目指して、任用要件・賃金体系を整えていきます。
まずは「キャリアパス要件Ⅰ」で求められている中身を確認する
キャリアパス要件Ⅰで求められている要件は以下のとおりです。
イ 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
このイ・ロ・ハのすべてを満たしていないと、どれだけ立派なキャリアパスの図や表を作っても、加算の取得要件を満たしているとは言えません。
結果として、実地指導で指摘を受けたり、最悪の場合は加算の返還につながるおそれもあります。
等級と職位を決めて「骨組み」をつくる
(1)等級(グレード)の段階を決める
最初のステップは、キャリアパスの階段=等級を決めることです。
- 例)1等級〜5等級
- 例)「新人」「一人前」「リーダー」「主任」「管理者」の5段階 など
等級が多すぎると違いが分かりにくくなり、年功的な運用になりやすくなります。
逆に少なすぎると、「がんばっても上がる段階がない」状態になり、やりがいを失わせてしまいます。
新人/一人前/リーダー/主任/管理者 のような「5段階」をベースに考えると、バランスが取りやすい事業所が多い印象です。
(2)等級ごとに職位を対応させる
次に、等級ごとに職位(役職名)を対応させます。
- 5等級:複数事業所を統括する所長クラス
- 4等級:単独事業所の管理者、あるいはスーパーバイザー
- 3等級:現場のリーダー・主任
- 2等級:中堅の介護職員
- 1等級:入職直後〜数年目の介護職員
といったイメージです。
| 等級 | 雇用形態 | 職位 | 主な業務・役割 | 任用条件(例) | 賃金体系(例) |
| 5等級 | 常勤 | 事業所責任者 | ・事業運営の統括 ・収支管理と人材マネジメント ・行政・地域との連携窓口 | ・管理職経験3年以上 ・関連資格保有 ・勤務シフトに柔軟に対応できる | ・基本給+管理職手当 |
| 4等級 | 常勤 | チームリーダー | ・部署運営の管理 ・業務改善の企画と実施 ・スタッフ育成・教育 ・関係部署との調整 | ・実務経験5年以上 ・職能資格保有 ・所内評価基準のクリア | ・基本給+役職手当 |
| 3等級 | 常勤・パート | 上級スタッフ | ・利用者支援の中心的役割 ・新人指導、後輩育成 ・複雑なケース対応 ・サービス品質向上の提案 | ・実務経験7~10年 ・専門資格保有 ・内部評価の一定基準を満たす | ・基本給+スキル手当 |
| 2等級 | 常勤・パート | 中堅スタッフ | ・標準的な介護業務を自立して実施 ・利用者の状態把握と報告 ・業務記録の作成 | ・経験2~5年 ・初任者研修修了 ・OJT評価一定基準 | ・基本給 |
| 1等級 | 常勤・パート | 初級スタッフ | ・基本的な介護サービスの習得 ・指導者のもとでの業務遂行 ・記録業務の補助 | ・入職後研修の修了 ・指導担当者からの評価 | ・基本給(入職初期の水準) |
職責・職務内容を定める
等級と職位を決めたら、次は「それぞれが何を担うのか」を具体的に言葉にします。
(1)代表的な職責・職務内容を書き出す
すべてを書こうとするとキリがありません。まずは
- 利用者支援(ケアワーク)
- チーム内の調整・指導
- 行政対応・家族対応
- 事業運営・目標管理
などの柱ごとに、「この職位ならここまで求める」という水準を、代表的な項目だけ書き出していきます。
例(イメージ):
- 1等級:指示を受けながら、基本的な介護業務を安全に行う
- 2等級:利用者の状態変化を捉え、必要に応じて上司に報告・相談する
- 3等級:難度の高いケースのケア方針をチームで検討し、後輩に指示する
- 4等級:事業所の運営方針・目標を設定し、スタッフに落とし込む
- 5等級:法人全体の事業戦略をふまえ、複数事業所の運営を統括する
このように、「等級が上がるほど
- 技術スキル
- 問題解決力
- チームマネジメント力
- 経営視点
が段階的に高まっていく」イメージを持つと整理しやすくなります。
任用要件をどう決めるか
次に、「その職位に任用するための条件=任用要件」を決めていきます。
(1)任用要件の主な材料
任用要件としてよく使われるのは、次のような項目です。
- 勤続年数・経験年数
┗ 前の等級で○年以上在籍、福祉・介護職員として通算○年以上 など - 資格・研修
┗ 介護福祉士、社会福祉士、初任者研修・実務者研修の修了 など - 研修受講歴
┗ 「○○研修を修了していないと2等級には上げない」など - 実務経験の幅
┗ 複数シフトの経験、委員会運営、行事企画、加算関連事務の経験 など - 人事評価の結果
┗ 一定期間、評価が下位になっていない/上位評価を継続している など - 昇格試験の結果
┗ 面接・レポート・実技・筆記試験 など
これらを組み合わせて、「この職位に上がるには、最低限ここまではクリアしてほしい」というラインを設定していきます。
(2)迷ったら「卒業方式」か「入学方式」で考える
昇格条件の考え方は、大きく2つに整理できます。
1.卒業方式(今の等級を「卒業」したら自動的に上がるイメージ)
- 入職直後〜数年目の介護職員のキャリアアップに向いています。
- 例)「2等級に3年以上在籍」「必要な研修を修了」「評価は概ね標準以上」
→ 条件を満たせば原則昇格させる。
2.入学方式(上位の役割に「合格」した人だけ上げるイメージ)
- 主任・管理者など、リーダー層以上の任用に向いています。
- 例)リーダー候補研修の受講+昇格面接+上位評価 などをクリアした人を「3等級リーダー」に登用する。
実務的には、一般職の等級アップは「卒業方式」、リーダー以上は「入学方式」とする事業所が多い印象です。
(3)成長スピードに応じた「飛び級」ルールも
任用要件に勤続年数だけを入れてしまうと
- 能力の高い方が「待たされている」と感じてしまう
- 逆に、勤続年数だけ長くても能力が伴わないケースが出てくる
という歪みが生まれます。
そこでおすすめなのが、「一定以上の評価・資格・試験結果がある場合は、必要年数を短縮できる」という「飛び級」ルールをあらかじめ決めておくことです。
例)
- 通常:2等級 →3等級には3年以上必要
- ただし、介護福祉士取得+評価Aを2期続けて取った場合は、2年で昇格可
こうしたルールを明文化しておくことで、「がんばれば早く評価される」というメッセージを出すことができます。
賃金体系をキャリアパスと結びつける
任用要件が整理できたら、次は賃金体系とのひも付けです。
(1)賃金体系の全体像を整理する
賃金は大きく「月例給」と「賞与」の2つに分けられます。
このうち月例給は、職務に対する基本的な報酬である基本給と、それを補うための各種手当で構成されます。
(2)基本給:等級ごとの「幅」を決める
基本給は、「その等級・職位に求める責任・難易度・必要能力」に応じて決める、ベースとなる報酬です。
キャリアパス表には
- 1等級:○万〜○万円
- 2等級:○万〜○万円
- 3等級:○万〜○万円
といった形で、等級ごとの目安レンジを載せておくと、職員が「昇格したときの将来の収入イメージ」を持ちやすくなります。
(3)各種手当を整理する
各種手当には、大きく分けて次の3つがあります。
- 稼働に応じて支払うもの(時間外手当、深夜手当 等)
- 職務・役割に応じて支払うもの(役職手当、資格手当 等)
- 生活条件に応じて支払うもの(通勤手当、住宅手当 等)
キャリアパスで焦点になるのは、このうちの「職務・役割に応じた手当(職務関連手当)」です。
キャリアパス表に載せることで
- どのような役割を担うと、どんな手当がつくのか
- 事業所として、どんな人材像に報酬を厚くしたいのか
を、職員に分かりやすく伝えることが大切です。
ここまで自力で整えるのは、正直かなり大変です
ここまで読んでいただいて
- 「やるべきことは分かったけど、これを全部ひとりで設計するのはムリ…」
- 「処遇改善加算の要件と、就業規則・賃金規程の整合性まで見る余裕がない」
と感じた方も多いと思います。
実際
- 現場のマネジメント
- シフト調整・採用・書類対応
- 各種加算の算定・実績報告
をこなしながら、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲや月額賃金改善要件まで設計するのは、中小規模の福祉事業所にとって相当な負荷です。
弊所で任用要件・賃金体系の整備まで伴走します
そこで弊所では、処遇改善加算を安心して算定できるよう、手続き代行と労務管理を一体でサポートする社労士顧問サービス「処遇改善加算まるごと労務サポート」をご用意しています。
このサービスでは、例えば次のような支援が可能です。
- 現在の就業規則・賃金規程・処遇改善加算の算定状況を一度棚卸し
- お客様の規模・サービス種別・職員構成に合った等級・職位・職責・任用要件・賃金体系の作成
- キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ、月額賃金改善要件を満たすための就業規則・賃金規程の見直し
- 実績報告・配分管理など、処遇改善加算まわりの代行
もちろん、上記に加えて、職員の入退社手続き、給与計算、算定基礎届、労働保険の年度更新といった社労士が通常行う業務もあわせて代行しています。
「うちのやり方はこのままで大丈夫か?」
「来年度の要件を見据えて、今のうちに何を直しておくべきか?」
といった不安を、一緒に1つずつ解消していきませんか?
まとめと次の一歩
任用要件・賃金体系(キャリアパス要件Ⅰ)の整備は
- 要件を正しく理解する
- 等級・職位の「骨組み」をつくる
- 職責・職務内容を言葉にする
- 任用要件を決める
- 賃金体系(基本給・手当・賞与)をキャリアパスとひも付ける
という流れで進めると、整理しやすくなります。
しかし、限られた人員で日々の運営に追われる中、これらを法令や加算要件と整合させながら設計するのは容易ではありません。
もし
- 「キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲの整備に手を付けられていない」
- 「今の任用要件・賃金体系で要件を満たしているか不安」
というお気持ちが少しでもあれば、一度、処遇改善加算と人事・労務をまとめて見直すタイミングかもしれません。
ご案内

福祉・介護職員等処遇改善加算の運用で、お困りのことはありませんか?
「処遇改善加算をしっかり活用して、職員の定着につなげたい」
「要件や提出書類の書き方がよく分からない」
「加算を使って職場環境をもっと良くしたい」
そんな事業所様に向けて、福祉分野での支援経験豊富な社労士が処遇改善加算の運用をトータルでサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください!